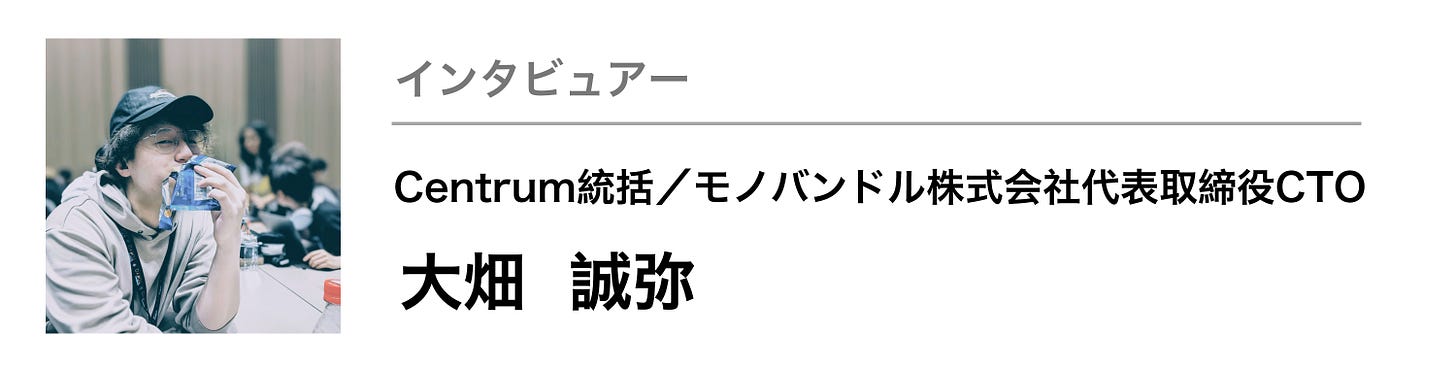Centrumでは、分散システムやブロックチェーン技術を活用した革新的なプロジェクトに取り組む方々をサポートしています。今回はCentrumをその立ち上げに活用している、DIMO Japan 代表の林さんにお話を伺いました。DIMOはブロックチェーンを利用して、車両データを共有・活用するプラットフォームを構築し、自動車業界に新たな風を吹き込もうとしています。
DIMO Japanの設立リリースはこちら:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000164070.html
■ 通信業界から自動車業界へ
—— 今までの林さんのキャリアや今までの道のりについて教えてください
私は元々通信業界の出身で、Web1.0の時代から現在に至るまでの、インターネットの発展を見てきました。その後Web2.0の時代になると、コンシューマーが自分たちで繋がっていく世界になっていきました。この中で私は、固定回線事業やモバイル回線事業の立ち上げ、CtoC取引サービスの日本事業立ち上げなど、様々なプロジェクトに携わっていました。
その後、日本の中古車の会社に入社しました。そこで「中古車流通×インターネット」の可能性を探る中で、アフリカでのマイクロファイナンス事業を立ち上げました。日本で安く手に入れた中古車をアフリカに送り、現地のドライバーからいくらか回収するモデルです。
日本の中古車をアフリカに送って、リターンが20%の金利で回っている金融商品のようなものです。不動産REITのような感じですね。
■ DIMOとの出会い
—— 自動車業界へ入ったあと、DIMOとはどのようにして出会うのでしょう?
アフリカの事業を運営している中で知り合いのベンチャーキャピタリストから「林さんのビジネスにWeb3の要素を入れてみるといいのではないか?」というアドバイスをもらい「車 x 通信 x Web3」を考える機会がありまして、DePIN(※)の領域で色々と調べたり人と話をしていく中で、DIMOに出会いました。
DIMOは、当時私がふわっと考えていたことについて、よくうまく考え尽くされたモデルで実現されているなと感じました。
※ DePIN … Decentralized Physical Infrastructure Networkの略。現実世界の物品やインフラをブロックチェーンで管理・拡張する仕組みやそのプロジェクトの事。
その後、DIMOのFounderに連絡し直接話すことができました。当時、Founderの元には様々なローカライゼーションの打診が来ていたようでしたが、私の自動車ビジネスの経験を元に議論をすることができ、DIMO Japanの設立に携わることになりました。
—— DIMOって、どんなプロジェクトでどういう経済圏を作ろうとしているんでしょうか?
DIMOは「みんなで車両データを共有し、みんなで利用できる基盤を作る」というコンセプトのDePINプロジェクトです。
利用者に車両データ(走行データや整備情報など)をブロックチェーンに上げてもらうことで、この基盤を構築します。この見返りとして、車両データを上げてくれた人にトークンを付与します。
—— なるほど、今はどれくらいの台数が参加しているのでしょう?
現在アメリカでは約18万台の車両が接続していて、そのうち約30%がEVです。
テスラなどのEV車はAPIで直接接続できますが、それ以外の車はOBD(※)デバイスを使用します。このデバイスを車のOBD端子に接続し、アプリとペアリングすることでNFTが生成され、車のデジタルツインが作られます。
※OBD … On-Board Diagnosticsの略、車の各種自己診断情報を取得できるシステム
物理的な車と唯一紐づいたデジタルツインに、車両データがどんどん蓄積されていきます。そのデータを共有してもいいというユーザーのデータは、保険会社や整備工場などが購入し、彼らのミニアプリを通じてサービスを提供します。
例えば、「あなたの運転を見ると、現在の保険料は半年で300ドル払っていますが、200ドルが適正だと思います」といった保険料の最適化や、「あなたの車は今、中古車市場に売れば残債を返済してもプラス1万ドル儲かりますよ」といった価値評価などのサービスをこのDIMOの仕組みを使うことで実現できます。
■ 日本市場への参入
—— DIMO Japanとして日本での今後の展開について、どのような領域から進めていく予定でしょうか?自動車業界には多様なステークホルダーが存在しますが、現時点で想定しているものがあればお聞かせください。
こういった取り組み自体はアーリーアダプター向けのものになるので、まずはテスラユーザーを中心に展開していき、徐々に対応車種を増やしていこうと考えています。テスラユーザーはその属性的にアーリーアダプターが多いですし、テスラ車はOBDデバイスが不要でAPIの連携に対応しているので、始めるハードルが低いんです。
アーリーアダプターの方々は、本当に好きなものを人に紹介するとか、心から面白いって思える物を世に出していく人たちだと思うので、そういった面でも相性が良いです。
またそれ以外にも今様々な計画が動いており、2025年中に複数のリリースを予定していて、2026年には独自アプリのリリースを目指しています。
—— ありがとうございます。確かにAPI連携が可能だとコストも低くできそうで良いですね!OBDデバイスを挿すための端子は全ての車に搭載されているのですか?
2008年以降の車には全部搭載されています。つまり2008年以降の車には全てOBDデバイスを挿すことができます。しかし、日本でしか流通していない車があったり、車種ごとにOBDに流れるデータのフォーマットが違ったりしていて、相互接続性に関する課題があります。これは日本市場の特徴として意識しないといけないポイントです。
日本は世界で見てもすごく独特な自動車市場が形成されています。世界に冠たる自動車大国なので、メーカーさんとwin-winの関係性を構築できるかどうか、これもとても重要ですね。
■ 標準化がもたらす未来
—— 実際の自動車メーカー各社は、DIMOのような自動車データを集めることのできる基盤を欲しているのでしょうか?彼らは独自に自社のデータを集める仕組みを作っているはずですよね?
まさにそこは我々も内部で常々話しているポイントです。
我々が提供できるであろう付加価値の中の一つに、サードパーティが自由に利用できるSDKやデータ基盤のようなものがあると考えています。
自動車業界は会社や部門ごとに分岐が多様にあって、サードパーティが全部の車・全部のデータを対象にして共通のアプリを作るのはとても難易度が高いです。全てが縦割りで、一つの会社の中でも部門ごとや車種ごとにサイロ化していますから。
携帯電話で例えるならガラケーの時代のような感じですね。当時iPhoneがでたばかりの頃はみんなが売れないといっていましたが、WWDC(※)の現地会場の開発者たちがめちゃくちゃ喜んでいたんですよね。「こんなデータが開示されるのか」「このインターフェースが用意されているのか」など、盛り上がっていたことを覚えています。
—— 当時のWWDC現地参加してたんですか!すごい!!
※WWDC … Appleが主催する Worldwide Developers Conference
そのような印象から、逆にデータが示されていない状態で、それをどう活用できるのかを考えるのはとても難しいということを感じました。
車についても、もし標準化されたインターフェースやデータが使えるようになったら、そこからインスピレーションを得たり「こんなこともできるかもしれない!」という熱量が生まれたりするんじゃないかと思っています。サイロ化されて縦割りで情報が標準化されていない状態から、標準化されたインターフェースやデータが使えるような状態を作る、といった面では、かなり意味があると信じています。
—— なるほど。データは、データとしてそこに置かれていないと利用できると気づかない、という性質を持つものだと思います。業界全体としてデータの可視性を高めることで、ロスも減らせるし、なにより開発者の熱量に繋げられるというコンセプトは素敵だと思います。
■ 日本の強みを生かして、自動車業界の変革へ
—— DIMO Japanで今後予定していることには、どんなものがありますか?
日本には、アメリカとは違った強みが明確にあります。それはコンテンツ文脈だったりゲーミフィケーション文脈だったり、多岐に渡りますが、アメリカとは明確に違う地盤であることは確かです。だからこそ、私は日本ならではのビジネススキームやアメリカとは違った掛け算ができるのではないか、と考えています。
具体的には、DIMOを活用した様々な施策を用いて、DePINの世界の可能性を提示するショーケースのようなものをしたいと思い、日々仕込みをしています。
車の詳細なデータが活用できるようになっても、それをクリエイターや開発者の方々が追いつき使いこなせるようになるまでには時間がかかります。日本のクリエイターや開発者の方々は優秀だと思うことが多いので、彼らとの関係性構築は大切だと考えています。
—— 最後に、DIMOの将来展望を教えてください
車は「コネクテッドになっていない最後のコンピュータ」とも言えます。あらゆるものが繋がった中で、部分的にしか繋がっていない最後のコンピュータです。
DIMOによって車がコネクテッドになると、人々のあらゆる行動変容が期待できます。
例えば、ブレーキパッドを必要以上に削ったり、日光に当てて塗装を劣化させたりすると、車両価格が大きく変わってくることを、人々は認識できていません。
こういったインセンティブ構造を人々の行動に反映させることができれば、DIMOの価値が証明されることになると思います。
おわりに
林さんは、通信の黎明期からインターネットそしてWeb3を見てきた視点から、Web3と車を結びつける可能性に手応えを感じているといいます。
「Web3の文脈で、車に戻って来れてよかったと思います。自動車の世界を経験していなかったら、DIMOの話に繋がらなかったでしょうから。」
DIMOおよびDIMO Japanの取り組みは、単なる車両データの活用にとどまらず、自動車業界全体の変革を促す可能性を秘めています。今後の展開に注目です。
DIMO Japan 代表 林さん、ありがとうございました!
■ 「DIMO」「DIMO Japan」とは
「DIMO」は、モビリティ領域におけるWeb3インフラを構築する米国発のスタートアップであり、車両データの収集・共有・活用を通じて新しいサービス開発を可能にするサービス提供基盤を提供する。利用者の主権を尊重し、分散型のエコシステム構築を進めている。2025年6月に日本法人「DIMO Japan」を設立し、世界有数の自動車産業を有する日本市場での本格展開を開始。
Official website: https://dimojapan.com/
■「Centrum」とは
「Centrum」は、2023年8月に渋谷駅前にオープンしたブロックチェーン・分散システム領域特化型のコミュニティスペースです。おもにコワーキングスペース・イベント会場等として、文化的資産の豊かな渋谷においてブロックチェーン・分散システム領域でのアジアのハブとなることを目指し、国内外のブロックチェーン・分散システム関連のスタートアップ企業やプロジェクト、またweb3領域との連携を試みる企業それぞれに価値を提供しています。技術者、起業家、イノベーターらが一堂に会し、新しいアイディアやプロジェクトを生み出すための空間を提供しています。
Official website:https://centrum.studio
2023年8月のオープン以降、月間約500名の方にご来館いただいており、累計来館者数は1.1万人を超えました。Centrumに関するご相談やご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
Centrumへのお問い合わせ:https://centrum.studio/contact
💭 Centrumについて コミュニティ / コワーキングスペース / イベントスペース
╭━━━━━━━━━━━━╮
👀 Centrumの最新情報をGET❕
╰━━━━━━━━━━v━╯